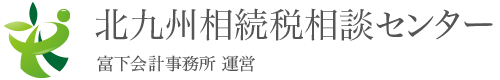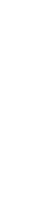相続税の税率と基礎控除の関係とは?計算方法と節税のポイント
- 2025年09月12日
- 相続税

相続税の税率と基礎控除の関係とは?計算方法と節税のポイント
こんにちは。相続が発生した際、多くの方が気になるのが「相続税がいくらになるのか?」ということでしょう。相続税額を計算するためには、「基礎控除」と「税率」の関係を正しく理解することが不可欠です。今回は、この2つの重要な要素に焦点を当て、相続税の計算方法と節税のポイントを解説します。
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、相続財産の総額から無条件で差し引くことができる非課税枠のことです。相続財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。いわば、相続税がかかるかどうかの「ボーダーライン」と言えるでしょう。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。法定相続人が増えるほど、控除額も大きくなります。
- 法定相続人:民法で定められた相続する権利を持つ人。配偶者は常に法定相続人となり、その他の順位は子→父母→兄弟姉妹の順です。
- 注意点:相続放棄をした人も、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含めます。
相続税の税率とは?
相続税の税率は、基礎控除額を超えた課税遺産総額に対して適用される税率のことです。日本の相続税は「累進課税」が採用されており、課税対象となる金額が高くなるほど、税率も段階的に高くなる仕組みになっています。
相続税の速算表
相続税額を計算する際の税率と控除額は、以下の速算表で確認できます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※この速算表は、法定相続分で分割したと仮定した各人の取得金額に対して適用されます。
相続税の具体的な計算手順
それでは、基礎控除と税率を用いて、相続税額を計算する具体的な手順を見ていきましょう。
ステップ1:課税遺産総額を計算する
まず、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いて、「課税遺産総額」を算出します。
課税遺産総額 = 相続財産総額 - 基礎控除額
※相続財産には、現金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も含まれます。
ステップ2:法定相続分で按分し、相続税の総額を計算する
次に、算出した課税遺産総額を、民法で定められた法定相続分で仮に按分します。その上で、速算表を使い、各人の「仮の相続税額」を計算し、それらを合計して相続税の総額を求めます。
【計算式】
(1) 課税遺産総額 × 法定相続分 = 各人の法定相続分に応じた取得金額
(2) 上記取得金額に速算表の税率を適用し、控除額を差し引く = 各人の仮の相続税額
(3) 各人の仮の相続税額の合計 = 相続税の総額
ステップ3:実際に財産を取得した割合で按分する
最後に、ステップ2で計算した相続税の総額を、実際に各相続人が取得した財産の割合で按分し、個々の納税額を確定します。
各人の納税額 = 相続税の総額 × (各人が実際に取得した財産の価額 ÷ 財産総額)
この計算方法を用いることで、誰がどれだけの税金を負担すべきかが明確になります。
基礎控除を活用した相続税対策のポイント
相続税を節税するためには、基礎控除の枠を最大限に活用することが重要です。
- 生前贈与の活用:年間110万円の非課税枠を利用して贈与を行うことで、将来の相続財産を減らし、基礎控除額を超える部分を少なくすることができます。
- 養子縁組の検討:法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額を増やすことができます。ただし、相続税法上の養子の数には制限がある点に注意が必要です。
- 不動産の活用:不動産は現金に比べて評価額が低くなることが多く、相続財産評価額を圧縮する効果が期待できます。
相続税対策は、個々の家族構成や財産状況によって最適な方法が異なります。専門的な知識が必要となるため、相続税対策を検討されている方は、ぜひ一度、税理士にご相談ください。適切なアドバイスにより、円満な相続を実現できるようサポートいたします。