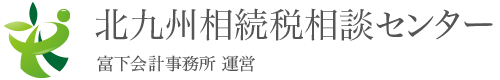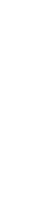知っておきたい相続税の基本
- 2025年04月30日
- 相続税
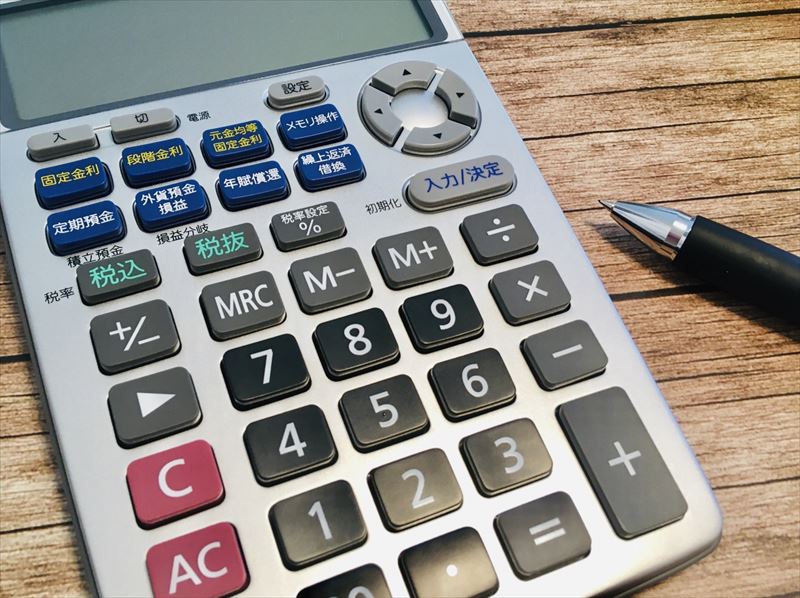
知っておきたい相続税の基本
相続税とは、亡くなった人の財産を相続した際にかかる税金のことです。
一定額以下であれば非課税ですが、財産が多い場合には高額な税負担になる可能性があります。
仕組みや控除を正しく理解しておくことで、不要な税負担を避けることができます。
相続税の課税対象となる財産には、土地・建物・現金・預貯金・株式などがあります。
一方、生命保険金の一部や、祭祀財産(仏壇・墓地など)は非課税です。
海外にある財産も、相続人や被相続人が日本に住所を持っていれば課税対象になります。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため注意が必要です。
また、申告が不要でも「相続税の基礎控除額」の範囲を把握しておくことが重要です。
相続税の計算方法と控除
相続税の基本控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
この金額を超えた遺産部分に対して課税されます。
課税される財産額が確定したら、法定相続分に応じて仮に分割したと仮定して税額を算出します。
そこから実際の分割割合に応じて、各相続人の納税額が決まります。
税率は10%〜55%と累進課税で、相続額が高くなるほど税率も上がります。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、法定相続分または1億6,000万円までは非課税です。
小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠など、複数の控除制度も用意されています。
事前に活用可能な控除を把握し、適切に申告することが節税につながります。
相続税対策としてできること
生前贈与を活用することで、相続財産を減らして相続税を抑えることができます。
毎年110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税になるため計画的な活用が有効です。
ただし、贈与契約書を作成し、贈与の実態を証明することが重要です。
不動産の評価額を下げることも有効な相続税対策の一つです。
賃貸物件にすることで評価額が下がり、相続税が軽減される場合があります。
ただし、不動産投資にはリスクも伴うため慎重に判断しましょう。
遺言書の作成も、円滑な相続とトラブル防止に役立ちます。
遺言によって明確に分割方針を示すことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
さらに、税理士や弁護士と相談しながら、早めに相続計画を立てることが大切です。