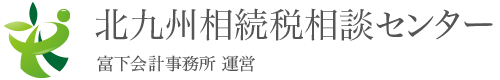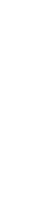贈与税とは?年間110万円まで非課税の仕組みを解説
- 2025年06月27日
- 未分類
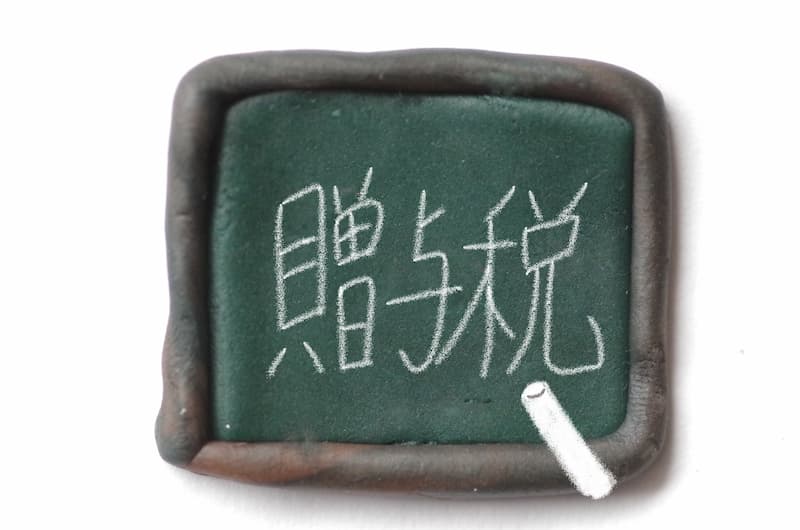
贈与税とは?年間110万円まで非課税の仕組みを解説
贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。親から子への金銭的な支援や、不動産・株式の譲渡なども対象になります。
特に「親からの贈与」はライフプラン上よくあるケースですが、年間110万円を超えると贈与税が発生する可能性があります。贈与をうまく活用すれば、相続税対策にもなります。
年間110万円まで非課税の「暦年課税」とは?
最も基本的な贈与税の制度が「暦年課税制度」です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この非課税枠は贈与者1人あたりに適用されるため、複数の人からそれぞれ110万円ずつ受け取ることも可能です。
贈与税の税率と控除額(暦年課税)
110万円を超える贈与には、以下のような税率がかかります。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※特例税率(直系尊属からの贈与)を使うと、20歳以上の子・孫に対して優遇されるケースもあります。
親からの贈与で使える特例制度
- 住宅取得等資金の非課税制度: 子や孫が住宅購入に充てる場合、最大1,000万円まで贈与が非課税となる(条件あり)
- 教育資金の一括贈与: 1,500万円までの教育資金を非課税で一括贈与できる(信託口座管理が必要)
- 結婚・子育て資金の非課税制度: 一定条件下で、1,000万円まで非課税(※制度は一部終了済。要確認)
相続対策としての贈与税活用術
親からの贈与を計画的に行えば、将来の相続税対策にもなります。特に「毎年110万円ずつコツコツ贈与する」ことで、相続財産を合法的に圧縮することが可能です。
ただし、「名義預金(形式だけ子の通帳)」や「一括贈与の分割見せかけ」などは、税務署に否認されるリスクがあるため注意が必要です。
贈与を受けたら申告が必要?
贈与税が発生する場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。申告は税務署への提出のほか、e-Taxにも対応しています。
110万円以下でも、非課税の特例制度を使った場合には申告が必要になるケースもあります。
まとめ:親からの贈与は計画的に
「贈与税 年間110万円」「親からの贈与」などのキーワードが気になる方は、将来的な相続も見据えた早めの対策が重要です。
制度の詳細は年によって変更されることもあるため、最新情報や具体的なシミュレーションは、税理士などの専門家に相談するのが確実です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については専門家にご相談ください。