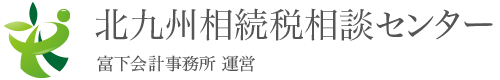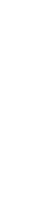相続税っていくらからかかるの?基礎控除や節税対策までわかりやすく解説
- 2025年06月27日
- 相続税
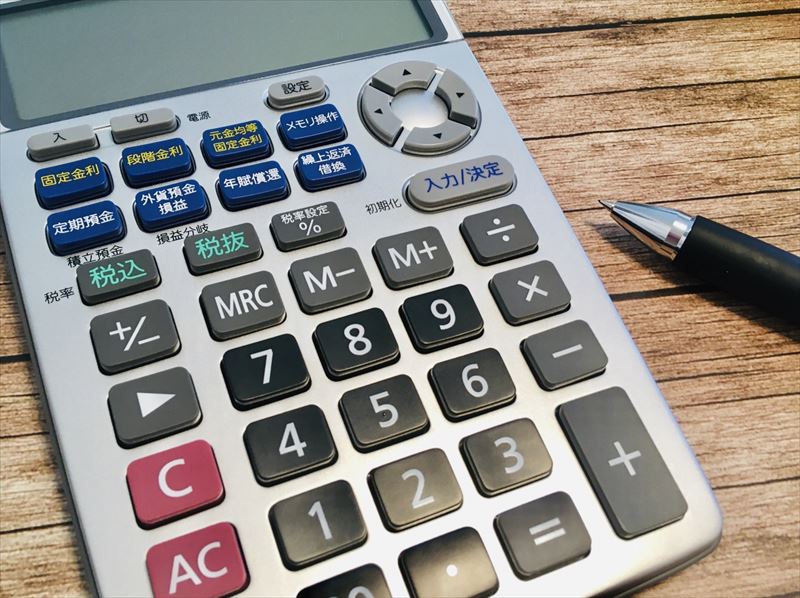
相続税とは何か?
相続税とは、故人(被相続人)の財産を相続または遺贈によって取得した際にかかる税金です。不動産、預金、有価証券、貴金属などの財産が対象になります。
相続人が複数いる場合は、それぞれの取得分に応じて課税されます。ただし、全ての相続に相続税が課されるわけではありません。一定の金額以下であれば非課税となります。
相続税がかかるラインは?基礎控除の仕組み
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、これを超えた財産に対して税金が発生します。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円となり、この4,800万円までは課税されません。
相続税の税率と計算方法
相続税は超過累進税率が採用されています。課税対象額が多いほど、税率が高くなります。
| 課税対象額(取得金額) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※上記は取得金額ごとの税率であり、正確な税額は法定相続分に応じた計算が必要です。
相続税の代表的な節税対策
- 生前贈与の活用: 年間110万円までは贈与税がかからない「基礎控除」を利用して少しずつ財産を移転できます。
- 生命保険の非課税枠:「500万円 × 法定相続人の数」までの死亡保険金は、相続税の課税対象から除外できます。
- 不動産の活用: 土地や建物は、相続税評価額が時価よりも低くなる傾向があり、現金よりも節税効果が期待できます。
- 養子縁組による法定相続人の増加: 基礎控除額が増え、非課税枠を広げることが可能になります。ただし、不自然な養子縁組は税務署に否認されるリスクがあるため注意が必要です。
相続を見据えた事前準備がカギ
相続税は、事後対応よりも事前準備の差で大きく結果が変わります。資産の棚卸しや相続人の確認、節税スキームの検討を早めに始めることが大切です。
税理士などの専門家に相談しながら、最適な対策を講じておくことで、円満な相続と税負担の軽減が実現できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断については専門家にご相談ください。